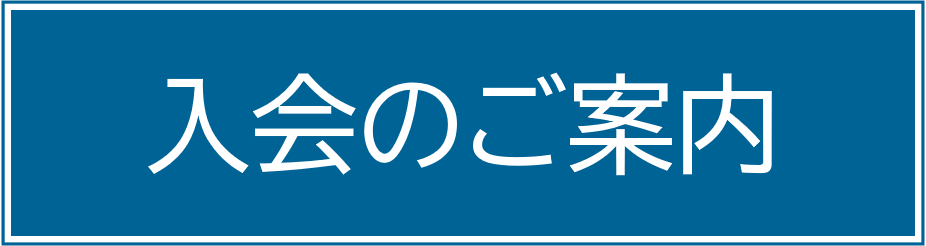第147号コラム:須川 賢洋 理事(新潟大学 大学院現代社会文化研究科・法学部 助教)
題:「二つの最高裁判例に見る動画配信」
今回は、ネットを利用した動画(テレビ番組)の録画・配信と著作権について思うところを書いてみたい。
さる1月18日、20日と最高裁判所は、ネットワーク上でのテレビ放送の再送信や録画に関して立て続けて判断を示した。一つは「まねきTV事件」(平成23年1月18日)であり、もう一つは「ロクラクII事件」(平成23年1月20日)である。どちらも原判決を破棄し、知財高裁に審議を差し戻している。
これらはどちらも、客から預かった地上アナログ放送の受信機械を都内に置き、ネットワークを通して客先に視聴させるサービスである。利用者はリモートで機械を操作し番組を視聴する。海外赴任者や地方居住者にはニーズがある故、ビジネスとして成立する。「まねきTV」は市販されているソニーの「ロケーションフリー」を大量に預かり設置しサービスを提供するものである(注:ロケーションフリーには録画機能はない)。また、「ロクラクII」はインターネット通信機能を有するHDDレコーダで親機(会社側設置)と子機(ユーザ側設置)からなるものである。
実はこの種のサービスに関する判例は他にもいくつかあり、この問題においての下級審判決は判断が分かれていた。「録画ネット事件」(知財高裁 平成17年11月15日)や「選撮見録(よりどりみどり)事件」(大阪高裁 平成19年6月14日)では、著作権侵害である旨の判決が出され、「まねきTV」と「ロクラクII」の下級審判決では侵害否定の判決が出ていた。最高裁はこれら二つの事例に関しても、著作権を侵害している旨の判断を示し、結果的に殆ど全てのテレビ番組のネット配信事業に関して、著作権侵害が成立するとの解釈になった。これらの事件は、一見すると番組のネット配信だけに限った問題のようにも思えるが、今後、各種クラウド事業や書籍の電子化代行サービスなどにも影響を与える可能性を秘めている。
その理由をいくつか挙げてみたい。
まず、「まねきTV」にしても「ロクラクII」にしても、そのコンテンツの
流れる道筋は1対1であり、大勢の人々に対するバラ巻き型のシステムではないということ。実は、この手のネットワークを利用したコンテンツ配信サービスでは常に「権利の侵害主体は誰か?」という点が議論され、「クラブ・キャッツアイ事件」(最高裁 昭和63年3月15日)という判例で使われた「カラオケ法理」というものが必ず出てくる。つまり、上記に筆者は「機器を客から預かった」と表現したが、これが「本当にただ預かっただけなのか?」、「業者が積極的に著作権侵害の行為主体として関与しているのか?」ということが議論されるわけである。今回の二判決でも裁判所はどちらも、機械を管理し、TVアンテナからネットワークへ番組を入力し、ロクラクIIに関しては録画する行為者は、サービス提供会社であるとしている。それ故に、公衆送信権の侵害になり、私的使用目的の複製にも該当しないと結論づけている。
さらに興味深い記述として、最高裁は「まねきTV判決」において、「自動公衆送信」について、『公衆の用に供されている電気通信回線に接続することにより、当該装置に入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置は、これがあらかじめ設定された単一の機器宛てに送信する機能しか有しない場合であっても、当該装置を用いて行われる送信が自動公衆送信であるといえるときは、自動公衆送信装置に当たるというべきである』と述べ、さらに、『当該装置が公衆の用に供されている電気通信回線に接続しており、これに継続的に情報が入力されている場合には,当該装置に情報を入力する者が送信の主体であると解するのが相当である』と判示しているところがあげられる。
以下は私的な感情論であるが、地方に暮らしている一市民として言わしてもらえば、テレビ局の数が少ないことは情報入手の点で甚だ不便なことであり、誰もが東京と同じ番組・チャンネル数を切望して止まない。地方局の経営、つまり広告収入料の安定を保護するためにその局数を制限されていることは、ユニバーサルサービスの面からしてみれば、不公平感に駆られるものである。そういった意味ではこの種のサービスは非常に社会的合理性があると言えよう。もっとも、(その善し悪しは別にして)そもそも著作権法は著作権者の保護を念頭においた法律なので、ユーザの利便性を前提に議論することは適切ではないのだが・・・。
しかしながら、放送局側の立場からものを見てみてもこの種のサービスを否定することは賢明なことだとは思い難い。例えば、かつてのアメリカでの有名なフェアユース判決に、「ベータマックス事件」(464 U.S. 417)がある。家庭用ビデオデッキが登場した時に、テレビ局や映画会社がソニーを訴えた理由は「ビデオデッキは我々の商売をあがったりにする」という言い分だった。しかし、現実はどうであろうか。テレビドラマや映画などのコンテンツ収入は、ビデオやDVD媒体等を利用した”リセール”なしには成り立たなくなっている。テレビ局にしても、いつまでも既得権益にしがみついているだけでは、放送と通信が融合したスーパーマルチチャンネル時代を生き抜くことは出来ないのではなかろうか。
【著作権は須川氏に属します】